3月17日に、大阪商工会議所主催で行われたセミナー「新たな医療機器開発が拓く在宅医療の未来」において、オンラインで事例紹介のお話をする機会をいただきました。
訪問看護×スマート医療機器で実現する“家で穏やかに”を支える新戦略〜 ともに未来を変える・東大阪プロジェクト 〜と題して、川邉綾香さんに依頼をいただいたものです、
大阪商工会議所の200社以上から申し込み
このセミナーには200社を超える企業から受講の申し込みがあり、大きな関心を集めました。基調講演は(株)メディヴァ コンサルティング事業部マネージャーの久富護先生による「在宅医療の概要と実際〜在宅医療機器の動向をふまえて〜」でした。
セミナーでは、慢性疾患の増加や高齢化に加え、コロナ禍を機に在宅患者が大幅に増加し、2023年には国内の在宅患者数が100万人を超えたこと、また医療機器の小型化やデジタル技術の進展により在宅医療機器市場が今後ますます拡大することが予測されていることが紹介されました。
東大阪市の現状とかわべクリニック
人口約48万人の都市、東大阪市でも要介護(要支援)認定者数は3万2000人を超え、その認定率は23%に達しています。このような状況の中、かわべクリニックでは2015年の開院以来、「最期は自宅で」「自宅に帰りたいと思った時が退院するとき」という患者さんの希望をかなえるため、在宅訪問診療と緩和ケアを主とした医療を提供してきました。

訪問看護師の役割そして課題とは
講演でまずお伝えしたのは、訪問看護師はどんな役割を担っているのか、そしてどんな課題があるのかということです。
訪問看護師の役割
- 医療的ケア(点滴、カテーテル管理、褥瘡処置など)
- 健康管理(バイタルチェック、病状悪化の早期発見など)
- リハビリ支援
- 精神的サポート
- 看取りの支援
病院と比べると、在宅医療でできる治療や検査には制限があります。しかし近年は、医療機器の小型化やデジタル技術が著しく発展したことなどから、自宅で使える機器やシステムの幅も広がっています。
訪問看護師だからこそ担えること
医師の指示のもとでの医療的処置や医学的知識に基づいた判断は、訪問看護師ならではの仕事だと言えます。それ患者さんの身体面だけでなく精神的・社会的側面も含めた全人的ケアが求められることも説明しました。
さらに患者さんのご家族に対しても、さまざまなアドバイスやサポートが求められます。普段から暮らしている生活の場におうかがいするからこそ見える課題、懸念などもあります。これは病院看護師とは異なる視点と言っていいでしょう。
訪問看護師の役割を担う新たな医療機器の可能性
在宅医療のニーズが増えている中で訪問看護師の数は絶対的に不足しています。これが最大の課題です。
そこで期待されるのは医療機器。在宅医療機器市場は、 今後ますます拡大することが予測されています。
- モニタリング機器やロボットによるバイタルサイン測定
- AI活用による異常検知システム
- 24時間見守り体制をサポートするセンサー技術
足りない人手をロボットやAIで補う手法は、医療や介護だけでなくあらゆる産業で必要になると言われており、今研究が活発に行われています。
「こんな医療機器があったらいいな」の声
事前に東大阪プロジェクトのメルマガ登録者の皆さんに「訪問看護の現場が求める次世代医療機器・装置」についてアンケートを実施し、多くの貴重なご意見をいただきました。
いくつか注目すべきアイデアを紹介します。

オムツの進化
- どのような姿勢でも横漏れしない
- 交換が簡易
- 排泄された瞬間に乾燥する
こうした高機能をオムツは、在宅医療の現場の苦労を劇的に軽減する可能性があります。
GPS機能付き小型マイクロチップ
認知症の方が迷子になってしまうケースが増えています。常に家族が付き添うのは難しく、警察や行政の負担も大きいため、今後より大きな社会課題になっていくことも懸念されます。
今もGPS付きの靴や腕時計などはありますが、取り外したり紛失したりするリスクはなくせません。
ペースメーカーのように体内に埋め込む技術があるなら、見守りにも活用できるのではないでしょうか。プライバシーや法律の面からすぐには難しくても社会的に受け入れられる可能性はあります。
服薬確認ロボット
薬の飲み忘れを防止し、実際に服薬したかを確認する機能がついたロボットがいてくれれば、服薬管理が難しい高齢者や認知症の方にとって、適切な時間に薬を飲むことにつながります。
音声で服薬時間を知らせるだけでなく、実際に飲んだか確認できる機能があるとより実用的っです。
既存の自動で薬を取り出せる装置「スマートピルボックス」や音声アシスタントと組み合わせると実現しやすいと考えられます。
服薬拒否や飲み間違いをどう防ぐか、介護者や医療機関と連携して、服薬情報を共有できるかもカギになりそうです。
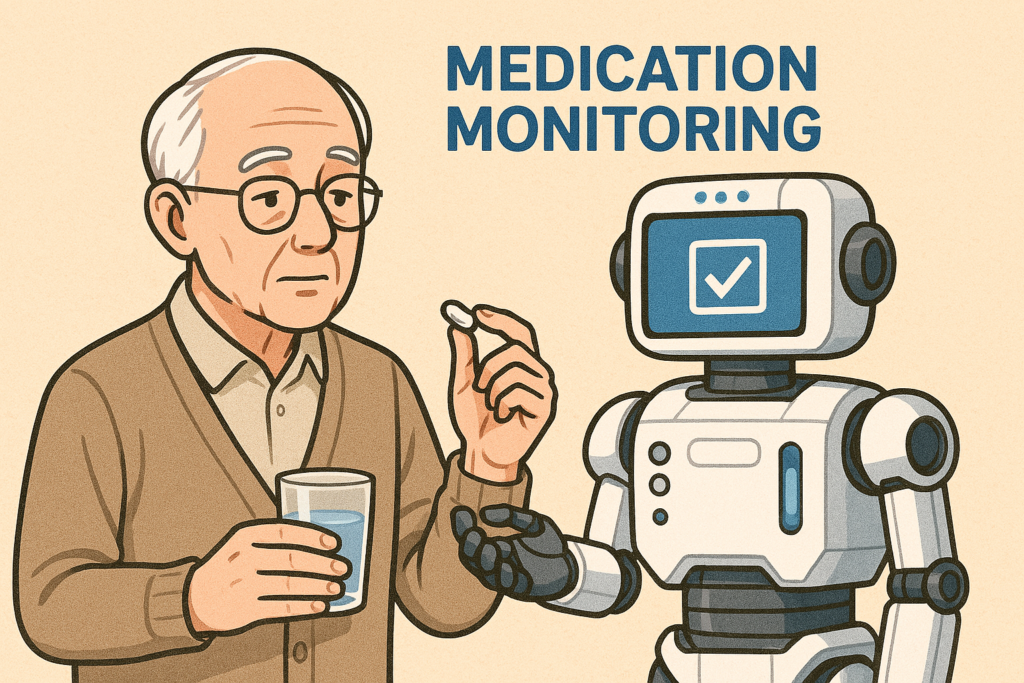
排泄モニタリングトイレ
排尿・排便の回数や量を記録することは健康管理の重要な指標です。便秘や脱水、腎機能の低下を早期に察知することにもつながります。
そこでトイレにセンサーを設置し、排泄量や回数を自動的に記録すれば、医療・介護者が状況を把握しやすくなります。すでに一部の介護施設では尿量センサー付きのトイレが導入されており、プライバシーの問題や、一般家庭にも普及できるようなコストにおさめられれば、機器メーカーとしてもビジネスチャンスになるものと思います。
大阪から在宅医療イノベーションを
訪問看護の現場で求められる、医療機器には、簡単な操作で誰もが扱いやすいことや壊れにくいこと、リアルタイムで情報共有できる通信機能などが求められます。
講演後には、「これまでの豊富なご経験に基づき、訪問看護師としてのお役割から、現場目線での求める製品まで、大変分かりやすいお話でした」との感想や、「本日ご提案いただいた製品を含め、企業様へのニーズ発表及び共同開発提案について、今後とも連携をさせていただきたい」とのお言葉をいただきました。
東大阪プロジェクトのクレドである「出会うことで人が動き出し、ともに未来を変える。穏やかなエンディングをみんなで」を実現するためには、医療と介護だけでなく、多くの職種や企業との連携が不可欠です。特に独自の技術をもったメーカーさんや、加工技術をもった工場、医療機関とのつながりがあるディーラーさんなどは、重要な存在です。
大阪商工会議所に加入されている多くの企業の皆様と連携することで、現場のニーズに即した革新的な医療機器の開発が進み、患者さんが安心して自宅で暮らせる環境づくりに貢献できると確信しています。大阪から在宅医療のイノベーションを起こし、高齢化社会の課題解決に向けた新たな一歩を踏み出していきたいと思います。
東大阪プロジェクトでは今後も様々な活動を通じて、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでまいります。皆様のご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします!

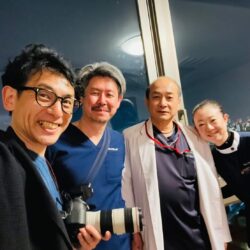





-700x400.png)


