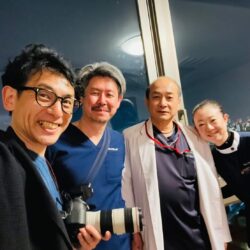東大阪プロジェクト事務局のいんちょ(院長)こと川邉正和です。
「仕方がない」から「自分もなにかできるかもしれない」、「仲間となら一緒にできるかもしれない」へ変革しよう。そんな希望を求めて参加したコミュニティ・オーガナイジング・ワークショップの参加者から届いた、とれたての想いを4回に分けてご報告してきました。
最終回となる今回は、東大阪プロジェクトのコアメンバーであり、昨年の「え~なぁEIWA EXPO」実行委員長を務めた山田貴弘さん(やまちゃん)の感想をご紹介します。グリーフケアの実践者として長年活動してきた彼が、コミュニケーション・オーガナイジングの理論と出会って得た気づきとは。
ぼんやりしていたものが形になった2日間
山田貴弘です。皆さんからは「やまちゃん」と呼んでいただいています。
いきなりちょっと抽象的な表現に思われそうですが、これまでぼんやりしていたものが輪郭を形成し、線になり面になるという体験ができた2日間でした。私がこれまで無自覚、無意識に行ってきたメッセージカードの取り組みを、コミュニティ・オーガナイジング(CO)の学びに当てはめてみると、とてもしっくりきたのです。

独りで始めた取り組みが会社全体へ
2019年から、私はご遺族のグリーフケアのために医療・福祉職へメッセージカードを依頼する取り組みを続けています。最初は独りで始めました。
共に行動したい人々(リーダーシップチーム)は、同僚や上司でした。取り組みを一緒にやろうと熱弁し、同僚が「一緒にやろう」と言ってくれました。結果として上司を動かし、会社の取り組みになり、リーダーシップチームができました。
医療・福祉職の方々(同志)に「思い出の共有」という資源を提供していただくために、稚拙ではありながらパブリックナラティブを語ることで、共感と協力の輪が広がり、2019年から現在に至るまで続けてこられる取り組みとなったのです。
私のパブリックナラティブを振り返る
今回の学びを通じて、自分の活動を改めて整理してみました。
ワークショップで学んだ「パブリックナラティブ」という手法。最初は難しそうに聞こえましたが、実は私がずっとやってきたことでもあったのです。
これは、人を巻き込んで一緒に行動してもらうための「3つの物語」を語る方法です。

ストーリー・オブ・セルフ(自分の物語)
まずは、自分自身の物語。なぜ私がこの活動をしているのかを伝えるものです。
私の場合、葬儀の現場で何度も目にしてきた光景がありました。悲しさ、寂しさを誰かに聞いて欲しい、分かって欲しいと願うご遺族。でも最近は、家族以外が参加しない家族葬を選択する方が増えて、その想いを共有する機会が失われていました。
「このままではいけない。何かを変えたい」
そんな感情の変化が、私を突き動かしました。ただ葬儀を執り行うだけじゃなく、ご遺族の心に寄り添える仕組みを作りたい。それが私のメッセージカード活動の原点です。これを医療・介護・福祉職の方々に聞いていただくことで「この人は本気で遺族のことを考えているんだ」と感じてもらえたのではないかと思います。
ストーリー・オブ・アス(私たちの物語)
次は「私たち」の物語。これは、聞いている相手と自分が共有している価値観や体験を思い出させる物語です。
葬祭ディレクターである私と、医療・介護・福祉に携わる皆さんの立場は違えど、実は同じ想いを持っていました。それは「遺族のグリーフケア」が大切という共通の価値観です。
医療・福祉職の方々も、患者さんが亡くなった後に残された家族のことを気にかけていました。「あのご家族、大丈夫かな」「何か自分にできることはないだろうか」──そんな想いを持っていることを知りました。
そこで私は語りかけました。「最期まで寄り添った患者さんのご家族が、その後どうしているか気になっていると皆さんも感じているはず。でも、その後の様子を知る機会はなかなかないですよね。それは、葬儀も同じことです。だからこそ、私たちは一緒にご遺族の心を支える可能性があるのではないでしょうか」
この「私たち」という感覚が生まれたとき、協力の輪が広がり始めました。
ストーリー・オブ・ナウ(今の物語)
最後は「今、行動すべき理由」を伝える物語です。これには緊急性と具体的なアクションが必要です。
私が伝えた緊急性は、葬儀までの限られた時間でした。人が亡くなってから葬儀まで、本当に短い時間しかありません。その刹那に故人との思い出を振り返り、心の整理をつける必要があります。この貴重な時間を逃したら、もう二度とチャンスは来ません。
だから具体的なアクションとして、「患者さんとの思い出をメッセージカードに書いて送ってください」とお願いしました。難しいことではありません、人生の短い時間しか接することはなかったかもしれないけれど、その間に生まれた思い出をただ書いて送るだけです。でもその一枚のカードが、ご遺族にとってどれだけ大きな支えになるでしょう。
「今すぐ始めないと、また一人のご遺族が孤独な別れをすることになります。一緒に始めませんか?」
なお戦略的ゴールは、これから先も決して乗り越えることができない死別による悲嘆(グリーフ)とうまく付き合っていくために、心残りのないお別れの場を提供することでした。
無意識から自覚へ──本当の学び
次のように考えると、2日間の学びを通じて全てがつながったように感じました。
これが無意識・無自覚ではなく、しっかりと自覚した状態でできることが肝心なんだと分かりました。今まで直感的に行ってきたことに、理論的な裏付けがあることを知り、今後はもっと戦略的に、意識的に活動を展開できると確信しました。
2日間演習をたくさんやったせいか、脳が汗をかき、2日目終了後は布団に入るやいなや爆睡し、朝まで一度も起きることはありませんでした。それだけ濃密な学びだったということです。
-1024x768.jpg)
八尾プロジェクトに持ち帰るという使命
今回の参加にあたり、いんちょより八尾プロジェクトの高松さんの代理として臨み、その学びを八尾プロジェクトのために還元してほしい、活かしてほしいという使命をいただいていました。
微力ではありますが、学んだことを代表の高松さん、リーダーシップチームに共有していきたいと思います。地域を超えた連携の中で、コミュニティ・オーガナイジングの力を活かしていけることを楽しみにしています。
EXPOでの経験──温かさとユーモアを忘れない
少し話は変わりますが、昨年の「え~なぁEIWA EXPO」での経験も、今回の学びとつながっているように感じます。
実行委員長として、東大阪プロジェクトが主催する中でも最大の市民向けイベントを無事に開催できました。イベントスタッフも市民の皆さまも心から楽しんでくださり、自然と笑顔が広がり、会場全体が温かい雰囲気に包まれました。とても心地よく、穏やかな空間が生まれた瞬間でした。
入棺体験のブースを出店させていただいた時は、当初不安でいっぱいでした。しかし、体験を終えた方々が皆笑顔でポジティブな感想を寄せてくださり、私も心から安堵しました。あの体験もまた、私たちが角度を変え、手段を変えて、人々が「別れ」について知り、話し合うきっかけになると思っていますし、ゴールに近づく一歩なのだと思います。

これからの実践に向けて
東大阪プロジェクトのクレドである「出会うことで人が動き出し、ともに未来を変える~穏やかなエンディングをみんなで~」というクレド(信条)が、ただの夢物語ではなく、現実に実現できるものだと確信する瞬間が何度もありました。
ワークショップで得た知識と、これまでの実践経験を組み合わせることで、より効果的な活動ができると確信しています。グリーフケアという重いテーマを扱いながらも、温かさとユーモアを忘れずに、地域の人々とつながり続けていきたいと思います。
まとめ
いんちょより、今回の総括です。
やまちゃんの感想から見えてくるのは、実践者が理論と出会うことの大切さです。長年、直感的に行ってきた活動が、COJの理論によって体系化され、より意識的で戦略的な活動へと昇華されていく──その過程が生き生きと描かれていました。
「無意識から自覚へ」という気づきは、多くの実践者にとって励みになるはずです。すでに地域で活動している人も、これから始めようとしている人も、理論を学ぶことで自分の活動をより深く理解し、効果的に展開できるようになるのです。
4回にわたってお届けしたCOJワークショップ参加者の感想シリーズ。それぞれが異なる立場から、異なる気づきを得ながらも、「人とつながる力」「変化を起こす力」を共に学びました。
東大阪プロジェクトは、これらの学びを活かし、地域の中で確実に変化を生み出していきます。