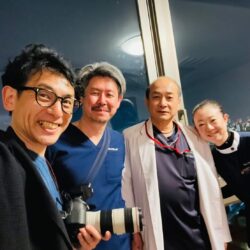サッカースタジアムの横に置かれた棺桶の中にはなぜか私。その蓋が閉じられた瞬間、予想もしなかった静寂に包まれました。朝一番の飛行機で羽田から駆けつけた甲斐があったと思える、特別な体験であると同時に、この特別感を伝えることの難しさも感じていました。そして、東大阪プロジェクトの仲間たちが目指す「真の地域包括ケアシステム」への思いが、より鮮明になったようにも思います。
イベントの概要は、前編にまとまっていますので、あわせてお読みください。
棺桶の蓋が閉じた瞬間に感じたこと
私も入棺体験をさせてもらいました。
棺桶に横たわり、蓋が閉じられた瞬間の感覚が今も体の表面に残っています。この世から遮断されるような、独特の静寂。聞こえなくなる音、見えなくなる光。
すぐに蓋を開けてもらったので、短い時間ではありましたが、実際にお経を読んでもらい、送り出される感覚を体験しました。もしあの中に30分、いや10分いたら、もっといろんなことを考えたのでしょうか。それとも「無」に近づいたでしょうか。

「棺桶で遊ぶなんて、死への冒涜だ!」と憤る人もいるかもしれません。しかし、決してふざけているのではなく、茶化しているのでもありません。普段なかなか向き合うことのない「死」について、無理やりにでも体感する機会として、極めて優れた装置だと感じました。

いざという時、自分の大切な人の将来や人生を考える一つのきっかけとして、非常に意味深い体験だと、自分で味わったからこそ断言できます。この日、東大阪プロジェクトのテントが並ぶ、向こうの端では胎内体験も行われています。「生と死」が絶え間なく連続してこの世は成り立っているのだと感じさせる、このメッセージ、スタジアムを訪れた多くの方が受け取ってくれたことを願います。
自分の最期は自分で選ぶ
この入棺体験の背景には、東大阪プロジェクトメンバーの山田さんの思いがあります。ある人が亡くなる時、なかば自動的に葬儀会社が決めた方法で送られるのではなく、自分が望む形で最後のセレモニーを行ってほしい。そんな選択する権利があることを知ってほしい。山田さんがこうした体験会のために運搬する棺に自らの身体を預けた人は、この日もおよそ百人にのぼりました。

亡くなる場所も同じです。厚生労働省のアンケートでは6割の人が「最期は自宅で」と希望しているにもかかわらず、現実には7割が病院や介護施設で亡くなっています。この理想と現実のギャップを埋めるためにも、元気なうちから「自分の最期」について考え、家族と話し合うことが必要です。
でも再び日常に戻ると、家族と葬儀について話し合うなんてことは、そうそうできるものではありません。これもまた、現実だと思うのです。
次なる挑戦:医療者自身の死生観を深める
今回のイベントで改めて感じたのは、私たち東大阪プロジェクトの活動の広がりと深さです。短期間で11ブース・40人規模の体制を整え、それぞれが心から「みんなに知ってもらいたい」という思いで活動している様子は、本当に驚くべき姿でした。お付き合いや義理ではなく、自分の内面にある使命感の持つ力はすごいです。
そんな東大阪プロジェクトが次に仕掛けるのが、11月9日(日)に大阪樟蔭女子大学で開催される「医療デザインサミット2025」です。
医療デザインサミットは毎年、日本医療デザインセンターが開催する大きなイベントですが、今回のテーマは「ENDING DESIGN – 人生の終焉をデザインする」。このサミットは、医療者自身の死生観を深めることに焦点を当てます。
「私たち医療者は、他者の『死』と向き合うことが多いながらも、自身の死生観について深く考える機会が多いとは言えません」という問題提起から始まり、医療者が自らの死について語れなければ、社会に死を語る文化は根付かないと考えました。
東大阪が輩出した2人の先生が語る「さいごの授業」
医療デザインサミットで最大の注目は、東大阪市出身の2人の著名人による「さいごの授業」です。
緩和ケアのトップランナーである池永昌之先生(淀川キリスト教病院)と、生活経済ジャーナリスト・いちのせかつみ先生が、「もし余命半年と知った時、あなたは誰に、どんなメッセージを残しますか?」という問いに答えます。
さらに「越境ブレスト」では、業種・職種・組織を超えて参加者が混ざり合い、会場全体で大規模なブレインストーミングを行います。まさに東大阪プロジェクトが目指す「多職種連携」の究極の形です。
参加費無料!本気で地域を変える覚悟
これだけ充実したプログラムでありながら参加費が無料という点はぜひ強調したいと思います。東大阪プロジェクトの「さいごまで住みやすい街にしたい」という本気の思いの表れともいえます。
趣旨に賛同していただいた企業からの協賛によって本イベントは成り立っています。おかげさまで多くの企業様が名乗りを挙げてくれました。(現在も募集は継続中)9月のFC大阪とのコラボで一般市民に「死を考える」きっかけを提供し、11月のサミットで医療者自身の死生観を深める。この2つが循環することで、地域に「死を語る文化」を根付かせようとしています。
スポーツも人生も、みんなでつくるフィールド
花園ラグビー場から大阪樟蔭女子大学と場所は変わっても、東大阪プロジェクトが目指すものは変わりません。
「真の地域包括ケアシステム」の実現です。それは医療と介護だけでなく、すべての職種が輪に加わり、地域で暮らすすべての人が「最期まで自分らしく生きる」ことができる社会。FC大阪とのコラボレーションによって、また新たな一歩を示せたのではないかと思います。
今回の熱気と笑顔は、きっと11月9日の医療デザインサミットにもつながるはずです。東大阪から始まった小さな輪が、やがて全国に広がり、「地域包括ケアシステム」という言葉すら必要なくなる日が来ることを願っています。
人生もサッカーも、一人では成立しません。みんなでつくるフィールドが、健やかで美しくありますように。
医療デザインサミット2025の開催要項
- 日時:2025年11月9日(日)10:00-18:00
- 場所:大阪樟蔭女子大学
- 参加費:無料
- テーマ:ENDING DESIGN – 人生の終焉をデザインする
- 詳細・申込:https://mdc-japan.org/design-summit2025/